ウミガメの甲羅に付くカメフジツボ。その姿を見ると「かわいそう」「取ってあげた方がいい」と思ってしまいがちです。でも、むやみに取り除くことは、かえってウミガメを傷つけることになりかねません。この記事では、カメフジツボとウミガメの不思議な共生関係と、私たちができる見守り方をわかりやすく紹介します。
フジツボの基本知識と特徴
海辺の岩場でよく見かけるフジツボ。その形状から貝の一種かと思われがちですが、じつは貝の仲間ではありません。エビやカニと同じ甲殻類の仲間なんです。白くて固い殻の中から手を振るような動きで、餌を集める小さな生き物・フジツボ。どんな生き物なのか、詳しく見ていきましょう。
意外と知らない!カメフジツボの正体
ウミガメの甲羅にはたくさんのフジツボの仲間のカメフジツボが付いています。このカメフジツボの付いた状態を見ると、ウミガメの健康状態がわかります。
専門家はカメフジツボの付着の様子から、ウミガメの体調や生活環境を調べています。カメフジツボとウミガメの関係はお互いの健康に深く関わっているのです。
カメフジツボってどんな生き物?
ウミガメの甲羅に住むカメフジツボは、一般的なフジツボと違い、ウミガメに完全に適応した特別な生き物です。
普通のフジツボの体の上部には、からだを守る2組の小さな殻があり、「蓋板(ふたいた)」と呼ばれています。しかし、カメフジツボには「蓋板(ふたいた)」がありません。ウミガメと共存する進化の過程で退化したのです。
カメフジツボの「蓋板(ふたいた)」が退化したのは、ウミガメの甲羅という特別な環境で暮らすようになったからです。 普通のフジツボは、ヒトデなどの敵から身を守ったり、干潮で水から出たときに乾燥を防いだりするために、貝のような「蓋板(ふたいた)」が必要です。
ウミガメの甲羅の上なら敵に襲われる心配もなく、いつも水の中にいるので乾燥する心配もありません。そのため、ウミガメと一緒に生活する進化のなかでふたの役割をする部分が退化しました。
また、普通のフジツボと違って、ウミガメの甲羅の上をじりじりと動くことができます。1頭のウミガメに数十個のカメフジツボが付いていることもあります。
なぜウミガメとカメフジツボは一緒に暮らしているの?
生まれたばかりの赤ちゃんカメフジツボは、海中を自由に泳ぎ回って住みかとなるウミガメを探します。最大で長径10センチメートルまで成長することがわかっています。
カメフジツボは、ウミガメの甲羅を住みかにして世界中の海を旅します。ウミガメが海の中を泳ぐと、海中のプランクトンを食べることができます。水面から出ると殻にこもり動きませんが、ウミガメが海中に潜ると活動を始めます。
フジツボがたくさん付着するとウミガメの動きが鈍くなったり、目や鼻が覆われて生活に支障が出たりすることもあります。
しかし、健康なウミガメの場合、フジツボの付着は自然な状態で、むしろ甲羅の掃除をしてくれる「おそうじやさん」として活躍してくれます。
このように長い時間をかけて、お互いに助け合う関係を築いてきたのです。
カメフジツボの驚くべき生存能力
ウミガメ の甲羅にはたくさんの生き物が住んでいますが、その中でも特に注目なのがカメフジツボです。
カメフジツボの捕食方法
カメフジツボは曼脚(まんきゃく)という触手のような脚を使って餌を捕ります。ウミガメが海中を泳ぐと、手招きするような動きでプランクトンを集めて食べます。
水面から出ると殻にこもって動きませんが、カメが潜ると活発に餌を求めて活動を始めます。
この捕食方法は、ウミガメの泳ぎ方に合わせて効率的に餌を取れるように進化したと考えられています。深さ300メートルの海底まで潜っても生きていける強さも持っています。
甲羅上での移動能力
カメフジツボは驚くべき能力を持っています。2年間で約10センチメートルも移動できます。アメリカでは餌を効率よく採るために、ウミガメの尾部から頭部方向へ、日本では頭部から尾部方向への移動が確認されています。
この移動能力は、江戸時代の本草画にも記録が残されているほど古くから知られていました。移動する理由はより良い餌場を求めることと考えられています。
この特殊な移動能力は、水中接着剤の開発などの技術の応用の可能性も秘めています。
カメフジツボがウミガメの健康に与える影響
カメフジツボの付着は、ウミガメの健康状態を知る大切な手がかりになります。ウミガメは、カメフジツボと一緒に生きていけるように長い時間をかけて特別な能力を身につけてきました。
ウミガメの特別な治る力
最近の研究で、ウミガメは驚くべき治る力を持っていることがわかりました。カメフジツボが付着すると、甲羅の骨に小さな穴ができることがありますが、ウミガメはとても早く修復することができます。
普通の動物は骨が治るまでに時間がかかりますが、ウミガメは特別な方法で素早く修復できます。この能力は、外敵から攻撃を受けやすい環境で生きるウミガメが進化の過程で身につけた大切な能力です。
健康なウミガメと病気のウミガメの違い
元気なウミガメの場合、カメフジツボは甲羅の上に均等に広がって付いています。研究によると、3000個以上ものフジツボが付いていても、元気に泳ぐウミガメがたくさん見つかっています。
しかし、具合の悪いウミガメは、カメフジツボが一箇所に密集したり、普段は付かない場所にまで付いたりしています。
ウミガメの泳ぎへの影響
健康なウミガメはカメフジツボが付いても、自分でこすりつけて落としたりして普段通り泳ぐことができます。
しかし、カメフジツボがたくさん付くと、動きが少し遅くなったり、甲羅以外の柔らかい部分まで付着すると泳ぎに支障が出たりすることもあります。
特に体が弱っているウミガメの場合は、カメフジツボの重みで泳ぎが遅くなり、餌を取ることが難しくなったり、敵から逃げられなくなったりすることがあります。
カメフジツボが甲羅以外に付くときの危険性
カメフジツボは、その名の通りウミガメの甲羅にしか付きません。多いときには1頭のウミガメに数十個も付いていることがあります。甲羅にカメフジツボが付着しても通常はウミガメに痛みを与えません。
むしろ、カメフジツボが甲羅の掃除をしてくれる良い面もあります。しかし、甲羅以外の柔らかい部分に付くと、ウミガメの生活に支障が出ることがあります。
カメフジツボは付着するときに、宿主の表面にしっかりと固定するため、外皮や組織に侵入することがあります。
ウミガメの目や鼻の周りや、首の付け根などの柔らかい部分は皮膚が薄く、神経や血管が集中しているため、刺激されて痛みや違和感を感じやすい部位です。
そのため、視界が遮られたり、呼吸がしにくくなったり、皮膚が引っ張られたりして動きがさまたげられることで、不快感を引き起こす可能性があります。
さらに、傷口に細菌や病原菌がはいり感染症を引き起こすこともあります。
ウミガメとの遭遇時の保護活動と注意点
野生のウミガメを見かけることはとても貴重な体験です。しかし、適切な対応を知らないと、かえってウミガメを傷つけてしまう可能性があります。ウミガメとカメフジツボの関係を理解し、正しい接し方を学びましょう。
人間の介入が必要なケースの判断基準
健康なウミガメは、カメフジツボの数を自然に調整できます。しかし目や鼻の周りに大量のカメフジツボが付着している、傷口にフジツボが集中している、普段は付かない場所に異常に多く付いているなどの場合は、専門家による保護が必要です。
特に、泳ぎ方がぎこちない場合や、長時間水面で動かない場合は要注意です。カメフジツボが付いているからといって、自分で除去しようとするのはやめましょう。
保護が必要な場合の連絡先
怪我をしているウミガメや、具合が悪そうなウミガメを見つけた場合は、すぐに地域の水族館や海洋生物保護センターに連絡してください。専門家が適切な治療や保護を行います。
保護されたウミガメは、健康状態が回復してから海に戻されます。全国各地の水族館では、保護・救護のネットワークを作り、24時間体制で連絡を受け付けているところもあります。
まとめ
カメフジツボとウミガメの関係は、一見すると寄生のように見えますが、実は何百万年もかけて築かれた素晴らしい共生関係です。お互いを助け合う素敵な関係を築いています。 カメフジツボが付いているウミガメを見かけてもそれは自然な姿なのです。
大切なのはそっと見守ること。それが海の生きものたちにとって一番の応援になります。

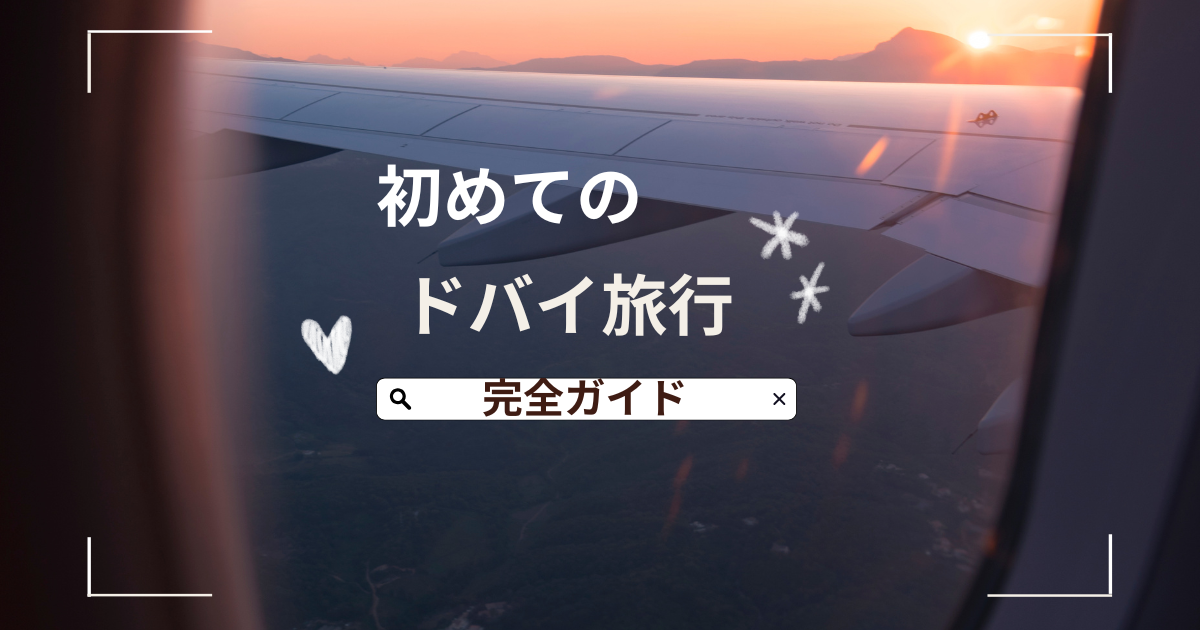

コメント